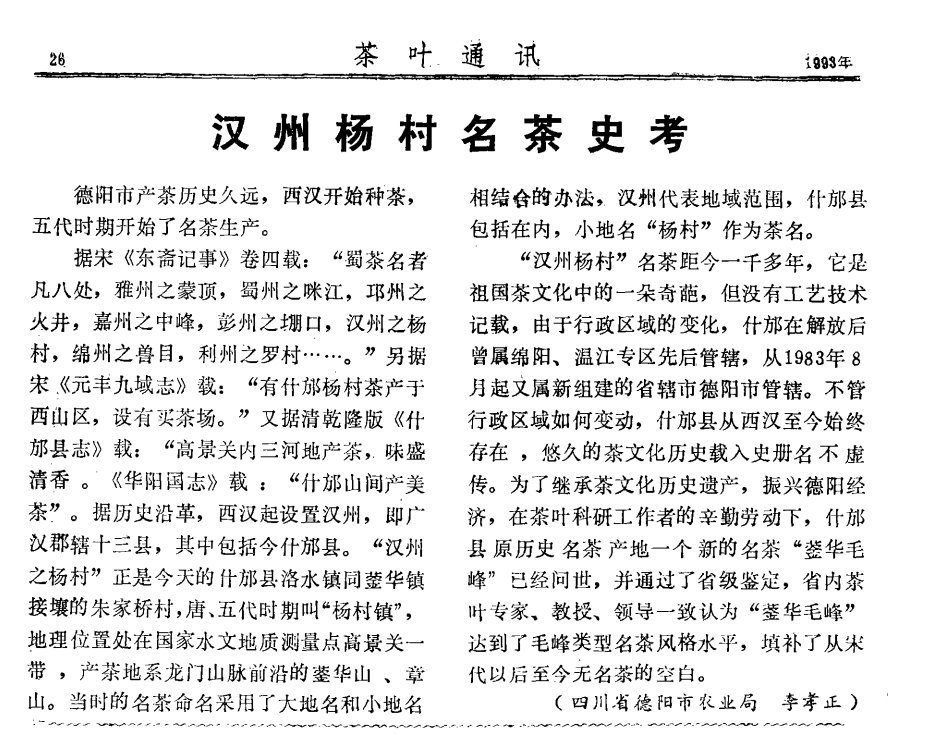
什方市は茶の生産において長い歴史を持っています。茶の栽培は前漢の時代に始まり、五代時代には有名な茶の生産が始まりました。
宋代の『東寨志』巻四には「四川茶の名所は八ヶ所あり、亥州の孟頂、蜀州の衛江、瓊州の火井、嘉州の中峰、彭州の張口、汾州の陽村、綿州の獣、麗州の羅村などがある…」と記されている。宋代の『元風九魚志』には「石坊市の陽村茶は西山区で産出され、茶屋もある」と記されている。清代の『石坊県志』乾隆本には「高井官の三河は、味が濃く香りの良い茶を産出する」と記されている。『華陽国志』には「石坊の山々で美しい茶が産出される」と記されている。
歴史の歩みによると、漢の時代に杭州が設立され、広漢郡は現在の十坊市を含む13の県を管轄していました。杭州陽村は朱家橋村で、現在の十坊市羅水鎮と映化鎮に隣接しています。唐五代には「陽村鎮」と呼ばれていました。地理的な位置は国家水文地質調査地点である高井観のエリアにあり、茶の産地は龍門山脈の最前線にある映化山と樟山です。当時、名茶の命名は大小の地名を組み合わせていました。杭州は十坊市を含む地理的範囲を表し、「陽村」という小さな地名が茶の名前として使用されました。杭州陽村の名茶は千年以上の歴史があり、中国茶文化のユニークな花です。



